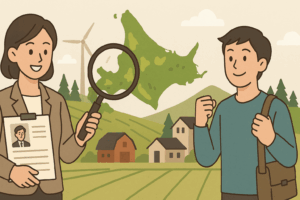9-1:2021・2025年改正点を専門家がやさしく要約
こんにちは。特定社会保険労務士の鶴木です。
2021年と2025年に施行されている労働衛生基準および熱中症対策の法改正は、企業にとって健康で安全な職場環境を築くうえで重要な節目となります。私は特定社会保険労務士として、27年間の国家公務員時代の労務・総務経験、および医療機関等での労務管理実務を踏まえ、これら改正のポイントと現場での活用法をわかりやすくお伝えいたします。
まず2021年の労働衛生基準改正についてです。大きなポイントは主に3つあります。
1つ目は照度基準の引き上げです。従来の最低基準は70ルクスでしたが、これが150ルクスに改定されました。これは単なる数字の変更に留まらず、高齢者や視力障害を持つ従業員の安全・健康に直結します。実際には作業エリアや通路での転倒事故防止、視認性向上に効果があります。多くの企業現場では、長年の慣れやコスト意識から照明環境の改善が後回しにされることが多く、私は照度計での現場測定を推奨します。数値として客観的に示すことで、経営層にも納得していただき、LED等の省エネ対応と合わせた改善が実現しやすくなります。
2つ目はトイレ設置基準の明確化です。小規模事業所(同時就業者10人以下)においては、男女別設置が原則ですが、「独立個室型」であれば男女共用も認められました。「独立個室型」とは壁・扉で完全に囲われ、内側からの施錠が可能なトイレです。この改正は小規模事業所にも性別を問わずプライバシー尊重の重要性が浸透した証ですが、実務上は老朽設備の更新や衛生管理の改善機会と捉えていただきたいと思います。トイレの快適性・清潔さは従業員満足度や採用力にも影響し、企業の「顔」ともいえる存在であることを常に忘れてはなりません。
3つ目は休憩室・休憩所の設備強化です。女性従業員が30人以上常勤する50人規模以上の職場では、男女別の休憩設備を整えることが義務化され、さらにプライバシー配慮のためシャワー設備等の整備指針が示されました。加えて、疲労回復のための休養室の随時利用推奨も改正項目に挙げられています。北海道のような寒冷地では冬季の室温管理も重要で、生産性や離職率低減への貢献が期待されます。ここでも現場実態を丁寧に把握し、従業員視点での使い勝手向上を目指すことが効果的です。
次に2025年6月に施行される熱中症対策関連の改正内容をご説明します。従来は努力義務の域を出なかった熱中症予防措置が義務化され、事業者責任が明確化される点が最大の特徴です。
具体的には、まず熱中症症状の自覚が困難な場合が多いため、異常に気づいた作業者や周囲の同僚が誰にどのように報告すべきか、報告体制の整備・周知が義務となります。これにより「自分だけが我慢すればいい」という職場風土を断ち切り、迅速な対応につなげます。また、離脱・冷却・医療機関受診の初期対応手順をマニュアル化し、全従業員へ周知しなければなりません。職場ごとに具体的な手順を定めることにより、慌てずスムーズに対応できる体制が求められています。
さらに、気温31度以上やWBGT値28度以上という数値基準で「高温状態の作業」が科学的根拠をもって定義され、重点的な対策対象となります。これは感覚や経験だけに頼らず、客観的データに基づく予防措置の確立を意味します。例えば、WBGT計や暑さ指数計の導入が増えるでしょう。
対策手段としては、「バディ制」の導入が推奨されています。これは2人一組で作業し、互いの体調変化に目配りするもので、筆者の登山経験からもわかる「相棒の目配りが命を守る」という考え方を企業現場に応用したものです。もはや孤立した作業は熱中症リスクを高めるため、仲間同士の見守りによる予防が不可欠です。
また、近年注目されるウェアラブル端末を活用し、体温や心拍数をリアルタイム監視する技術も有効です。体調の異変を数値で把握することで、早期休憩指示や医療対応につなげられます。導入コストはありますが、重大事故や労務トラブル回避のリスク低減効果を勘案すれば長期的には経営資源といえます。
以上、2021年の労働衛生基準改正と2025年熱中症対策の法令改正ポイントを解説しました。どちらも単なる「法令遵守」の枠を超え、従業員の健康確保と生産性向上、そして採用・定着力の強化につながる取り組みです。私は現場の声を丁寧に聴き、制度と実態の間に橋をかける役割として、事業所様の最適な対応策をご提案しています。
常に現場と対話し、不均衡な慣習や無理解による安全衛生の形骸化を防ぎながら、数値根拠による見える化とコミュニケーションをもって継続的な改善を推進していくことが求められます。今後も地域社会の皆様の安全衛生環境向上に貢献できるよう尽力してまいります。
9-2:よくある労務相談&トラブル事例と的確な初期対応
労務相談やトラブルは、企業と従業員の間で想定以上に多岐にわたり発生します。特に中小規模の事業所では、制度や規則だけでなく、現場の人間関係やコミュニケーションが絡むことも多く、問題の表面化が遅れてしまうことがあります。ここでは、私が長年の公務員経験および医療機関での多職種労務管理の現場から学んできた「よくある労務相談・トラブル事例」と、それに伴う効果的な初期対応のポイントについて解説します。
まず代表的な相談例としては「残業代の不払い疑義」「休暇申請のトラブル」「パワハラ・セクハラ」「メンタル不調による長期欠勤」などが挙げられます。これらは制度上の課題だけでなく、現場の運用や人間関係の摩擦から生じることが多く、その初期段階で適切に対応しないと、深刻な労務トラブルへ発展してしまいます。
例えば「残業代の不払い」という相談では、労働時間の管理方法の見直しや、法的に認められる時間外労働の範囲と照らし合わせた検証から始める必要があります。不払いに気づいた労働者側が直接交渉する場合、感情的になりやすく、双方向の信頼関係が崩壊しがちなため、外部の専門家の介入や早期アドバイスが重要な役割を果たします。私の経験では、まず労働時間の記録を丁寧に精査し、不明点があれば経営者側にも説明を求め、双方の認識のズレを初期段階で放置しないことがトラブル長期化防止につながりました。
次に「休暇申請のトラブル」では、特に有給休暇の取得に関する企業の消極的な対応や、時季変更権の運用が焦点となるケースが多いです。これに対しては、労基法の解釈はもちろんのこと、職場の実情を踏まえた柔軟な運用を促すことがポイントです。また、休暇について不満を抱く従業員に対しては、申請手続きや理由説明の負担を過剰に求めず、心理的安全が確保された相談窓口を設けることも有効です。
ハラスメントに関する相談は、特に繊細な対応が求められます。パワハラやセクハラは被害者が声を上げにくく、放置すれば職場環境の悪化だけでなく企業の信頼失墜に直結します。初期対応としては、被害者からの話を否定せず真摯に聴取すること、相談内容の秘密保持を徹底することが不可欠です。さらに、公正中立の立場で事実関係を収集し、必要に応じて第三者委員会や専門機関の介入を検討します。被害者が孤立せず、解決に向けて諦めない環境整備が重要です。
また、メンタルヘルス関連では、長期欠勤や休職に至る前段階での早期相談を促すことが社労士の重要な役割です。相談者の心理的負担を軽減するため、定期的な対話の場の提供や、医療機関・専門家との連携を進めます。職場復帰時には、段階的な勤務(段階的復帰)や職務内容の調整が必要となりますが、これを適切にサポートするには、経営側と本人、医師、社労士など多方面と綿密なコミュニケーションを図ることが求められます。
以上に共通するのは「初期対応の的確さと迅速さ」です。問題が表面化した直後は当事者双方の感情や認識にズレがあり、放置すると火種が大きくなります。効果的な初期対応は、以下のステップを踏むことが望ましいと私の経験が示しています。
- 問題の把握と精査:事実関係の収集に努め、双方の意見や記録を丁寧に聴取します。
- 中立的な姿勢での調整:当事者に対して公平であることを明確にし、感情的対立を緩和する努力をします。
- 制度・法令の的確な情報提供:お互いに法令や企業ルールの理解不足がないか確認し、わかりやすく説明します。
- 解決策の提示と合意形成:具体的な解決策を双方に提案し、合意を得るように支援します。
- フォローアップと再発防止策の検討:問題解決後も継続的に状況を把握、改善策の実効性を評価して、再発防止に努めます。
この手順を踏むことで、企業は労務トラブルの早期解決を図りつつ、従業員の信頼を損なうことなく職場環境の健全化を推進できます。
なお、初期対応の段階での「声を聴く姿勢」が最大のポイントです。日頃からのコミュニケーションが厚い職場ほど、トラブルが「小さな違和感」のうちに解消しやすいということは、私の登山経験にも通じるものがあります。山の厳しい環境下でも絶えず仲間との対話が安全と目標達成の鍵となるように、職場でも同様に相互の信頼と理解が重要です。
私が社労士として心掛けているのは、トラブルの一面だけで判断しないこと。労働基準法や労働安全衛生法に規定された権利義務の内容を踏まえつつ、個々の企業風土や人間関係の実態、さらには従業員一人ひとりの背景を尊重した現場主義です。そのためにも、常に経営者だけでなく従業員双方からの声に耳を傾け、双方の架け橋となって適切な解決をサポートしています。
問題を放置せず、初期段階での迅速な対応こそが、余計なコストと経営リスクを抑える最善の策であることを、この51年の経験の中で確信しています。労務トラブルは長期化すると精神的・時間的コストが膨大になるため、問題の初動の重要性を強調したいと思います。
そして、困難な状況でも、決して「諦めない」という姿勢を持つこと。労務課題は絶えず変化し、多様化していますが、一歩一歩着実に向き合い、解決策を共に探っていくことが、企業の持続可能な発展につながると強く信じています。
私、鶴木貞男は、北海道小樽を拠点に特定社会保険労務士・行政書士として、労務相談から労働衛生管理、ハラスメント対応まで幅広く対応しています。国家公務員時代の経験に裏打ちされた実務力と、医療機関で培った多職種対応力を活かし、相談者の悩みに寄り添いながら最善の解決策を提案いたします。そのため、どのような相談でも、まずはお気軽にご相談ください。信頼を得ることが、すべての問題解決の出発点です。