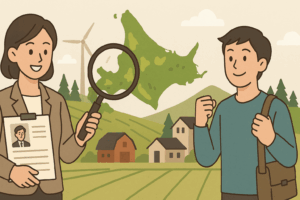前回は、北海道という地域特性や、私が社労士・行政書士の両資格を活かして契約書を見ているというお話をしました。今回はもう少し踏み込んで、雇用契約書を作成するときの基本ポイントについてお伝えします。
1. 社労士の視点:労働条件の明確化
労働基準法では、雇う側は労働者に「必ず書面で明示しなければならない条件」があります。
例えば…
- 労働時間(始業・終業の時刻、休憩時間)
- 賃金の額と支払い方法
- 休日・休暇
- 契約期間(有期か無期か)
これらがあいまいだと、後で「聞いてない」「そんなつもりじゃなかった」というトラブルの元になります。
特に北海道では、冬季の悪天候による休業や、繁忙期と閑散期の労働時間の差なども考慮して明記することが大切です。
2. 行政書士の視点:契約書の法的有効性
契約書は単に条件を書くだけではなく、法的に有効でなければ意味がありません。
例えば、契約書に書かれている条文が労働基準法や労働契約法に反していると、その部分は無効になります。
また、業務内容や勤務地の記載が抽象的すぎると、後に解釈の余地が生まれて紛争の火種になります。
私の行政書士としての仕事では、単語一つの選び方までこだわってチェックします。「〜するものとする」なのか「〜できるものとする」なのか、この違いが後々大きな意味を持つこともあります。
次回は、北海道ならではの雇用契約書の注意点、特に季節雇用や観光業など地域特有の契約形態についてお話しします。